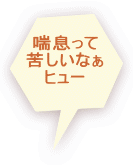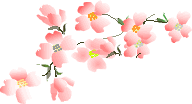
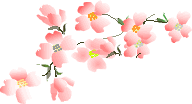
![]()
![]() 喘息ってどんな病気?
喘息ってどんな病気?
喘息とは慢性的に気道に炎症が起きている状態と言われています。
喘息は空気の通り道である気管や気管支の粘膜がはれて狭くなって、喘鳴(ヒューヒュー、ぜいぜい)、咳、痰、息苦しさ等の発作を起こす病気です。この発作によって呼吸困難が起こり、時には命に関わることもあります。しかし、発作のないときは普通の人と変わらない普通の生活ができます。
患者さんご自信やご家族の皆さんが、喘息について正しい知識を身に付け、正しく理解し、喘息発作を起こさないようにする治療をきちんと受けて自己管理(コントロール)ができるようにしましょう。
![]() 喘息ってどうして起こるの?
喘息ってどうして起こるの?
発作はごみや異物(花粉やほこりなど)、タバコの煙、などの刺激物を吸い込んだときや、細菌やウイルスなどの感染を受けたときに起こります。
喘息の患者さんでは健康な人に比べて僅かな刺激で、発作を起こしやすくなっています。
喘息の患者さんは気管支が炎症を起こして敏感になっているため、健康な人では感じない少しの刺激でもすぐに感じて、反応をして気道の平滑筋が痙攣して収縮したり、粘膜がむくんだり、粘膜からの分泌物が急激に増えたりするために、気道の内腔が狭くなって呼吸困難が起こります。このような状態を発作といいます。
気道に慢性的な炎症が起こるのは刺激に対して反応する粘膜に白血球の一種である「好酸球」が集まってくるためです。
好酸球は組織を破壊する強い作用を持っているため、これが集まってくると気道の粘膜を傷つけて脱落させ、さらに気道を敏感にします。
好酸球は多くの場合アレルギー反応の結果として集まってきます。しかし、こうした現象はアレルギーを起こす物質(アレルゲン)以外の刺激によっても起こることが解かっています。例えば風邪、(ウイルス感染)などが刺激となり好酸球が気道に集まってきて、非アレルギー性の慢性的炎症を起こすケースもあります。
![]() 発作の原因
発作の原因
喘息発作誘発の原因はさまざまで、個人によって異なります。しかし、大きくアレルギー性(アトピー性)のものと、非アレルギー性のものに大別することが出来ます。
アレルギー性の場合、アレルゲン(ダニ、動物の毛、ハウスダスト、食べ物、薬など)を吸い込んだり食べたりすることによって起こります。成人喘息では60%の患者さんが、小児喘息では90%の患者さんがアレルギー性と言われています。
発作の原因となる要因はさまざまで、個人によって異なり、また同一要因でもその時の体調や環境によっても違います。
ここでは一般的によく知られているものの一部を掲載します。
(1) ネコや犬などの動物の毛
(2) ほこり
(3) 花粉
(4) ダニ
(5) 花火・焚き火・線香などの煙・強い臭いのするものやスプレーなど
(6) 刺激性物質(たばこの煙・粉塵・排気ガスなど)
(6) 天気の変化(低気圧・台風の接近など)
(7) 気温・温度などの急激な変化
(8) ウイルス感染(風邪など)
(9) 運動
(10) 過労
![]() ピークフローPeak Expiratory Flow (PEF) 単位 l/min
ピークフローPeak Expiratory Flow (PEF) 単位 l/min
ピークフローとは、最大呼気速流量です。つまり息をどのくらいのスピードで吐き出せるかを測定します。ピークフローは思い切り息を吐き出すときの一番最初のひと吹きの部分です。ピークフロー値はピークフローメーターで測定します。
ピークフロー値を測定することによって次の事が解かり、客観的データとして治療に役立ちます。
① 自分の気道狭窄の程度がわかります。→気道の狭窄が起こると測定値は低下します。
② 吸入や薬剤の内服の前後に測定すると、その効果(どこまで改善しているか)が解かります。
③ 長期間記録をつけることによって、自分の喘息のタイプがわかり、また、次第に悪くなっているのか、改善し安定化傾向にあるのかなどが解かります。
④ ピークフロー値によって治療の目安が立ちます。治療方法の選択の根拠となります。低下の程度によって、薬の増量や病院へ行くタイミングなどがわかります。
⑤ きちんと測定しきちんと記録することによって、自己コントロールの指標となり、喘息死の危険を回避することが出来ます。
![]() ピークフローメーター
ピークフローメーター
何種類かのものがあります。
① パーソナルベスト
② ミニライト
③ バイタログラフ
④ アセス
⑤ フェラリスポケットピーク
など・・・。そのうち私の手元にあるものを写真紹介します。


左側がミニライト 右側がアセス
![]() PEFの測定方法
PEFの測定方法
① いつも同じ姿勢で測る。 まず立ってポインタや空気の穴に手が触れないように片手で器具を持ち、ポインタをゼロに戻します。
② 息を大きく吸いしっかりくわえて口の端から空気が漏れないようにして思いっきり強く息を吐きます。最初に思いっきり強く吹けば良い。肺活量計測と異なり最後まで長くふき続ける必要はありません
③ 1回だけではうまくいかないことがあるので2~3回ふいて一番良い値を記録する。
④ 喘息患者さんでは何度も吹けば気道が痙攣して値が次第に低下することが多く最初の値が最も高いことが多い。
![]() PEFの標準値と自己ベスト
PEFの標準値と自己ベスト
標準値は個人差があり、性別、年齢、身長によって異なります。計算式もありますが、器具を購入すると換算表がついてきますのでそれを参考にしてくださいね。
自己ベスト値とは毎日治療をしながらピークフローを吹いていくと調子が上がるにつれ高い値が出るようになります。自分の調子の良いときに出た最も高い値を自己ベストといい、記録しておきましょう。これは、その後の自分の調子を評価するのに役立ちます。
![]() ピークフローに基ずくゾーン表示
ピークフローに基ずくゾーン表示
%ピークフローの値で、貴方の今日の調子を色分けしています。 ●グリーンゾーン(青信号)
① 実測ピークフロー値が自己ベストの100%~80%。喘息の症状がなく調子の良いときです。予防薬を使用。
② 遊んだり、仕事や勉強が普通にできる。●イエローゾーン(黄色信号)
① ピークフロー値が自己ベストの80%~50%(あるいは80~60%)
② 軽い喘息症状があります(喘鳴・咳・胸が苦しいなど)
③ 小発作があるときもあります。
④ 治療の強化
⑤ 発作止めの薬を使う●レッドゾーン(赤信号)
① ピークフロー値が自己ベストの50%(60%)以下
② 中発作以上の発作があります。
③ 薬が効かない、息が苦しく早くなっている、歩けない、会話が途切れ途切れになる。
④ 直ぐにDrの診察を受けましょう。