
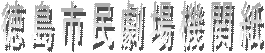
修の視点表紙へ戻る
*****************************************************************************************************************
 民藝『コラボレーション』2014.12.01発行
民藝『コラボレーション』2014.12.01発行
映画も演劇も、「ナチスもの」が好きで殆ど見ている。いつも胸の痛みを覚えつつも、「暗黒の時代」を繰り返してはいけないという強い思いと、「抵抗者」たちへの共感と感動が交錯するからだ。そして今回もまた、生涯記憶に残るであろう鮮烈な舞台となった。
1930年代のドイツでの実話。当代一と目される大作曲家が、若く才気あるユダヤ系作家との共同作業(コラボ)で新作オペラづくりに取り組む。しかし、ヒトラーとさえ面識があるほどの作曲家にも、政権からの冷酷で陰湿な圧力は強まるばかりだ。政権上層部と知遇を得ているからといって、何の防波堤にもならない。
刻々と悪化する時代状況に強い危機意識を持つ台本作家と違い、「ファシズム」を甘く考えていた作曲家だが、息子の嫁がユダヤ人という「弱み」を突かれ、ついには、孫をも守るために政権協力者になるしかない。もはや「どちらの側に立つか」といった選択の余地などないのだ。
数々の困難を乗り越え完成したオペラはすぐさま上演禁止になり、あげくベルリンオリンピックや日本紀元2600年などへの賛歌を作曲させられるまでに…。一方、迫害を逃れるために台本作家はブラジルへ亡命するのだが、終戦3年前に妻と共に服毒自殺…。
映画『戦場のピアニスト』でアカデミー脚色賞を得た原作者だけに、ナチス告発の眼は鋭い。政治に翻弄され抑圧される芸術家の苦悩が痛ましい。その名脚本に命を吹きこみ、圧巻の緊迫感あふれる舞台に仕上げた劇団の力量に感銘を受けた。
この舞台と前後して観た文化座『旅立つ家族』、二兎社『鴎外の怪談』もまた、期せずして、ファシズムの時代における「政治と芸術」の相克を描いたものだった。3本ともが、現代日本の政治状況を危惧し、「いつか来た道」への警鐘を鳴らすものといえる。時代を撃つ劇団や作家に敬意を表すると共に、僕ら観客もまた改めて襟を正したい。 (三宅 修)
*****************************************************************************************************************
2014.07.22発行 白い夜の宴(民藝)
白い夜の宴(民藝)
大企業社長の「誕生会」の一夜、家族の感情のズレや親子関係の歪みがサスペンスタッチで展開、最後まで観客をひきつける。「社会の矛盾」に面した時の、「しなくてもいいことをする」大切さ、「宿命」で片づけるな、というような社会派作家・木下順二の「魂」が伝わる屈指の舞台となった。
おかしな二人(テアトル・エコー)
離婚した親友同士が同居生活を始め、性格と生活スタイルの違いから起こるイザコザとドタバタ。爆笑の連続だ。役者はみんな達者で、観客を楽しませようとのサービス精神が噴出、特に、雨蘭咲木子の「ヘン顏」は見もの。ここまでやれる女優はそういない。大拍手!
先生のオリザニン(俳優座)
『樫の木坂四姉妹』の堀江安夫の新作。真面目な学者の功績に光を当てる真面目な舞台。ビタミンB1を発見した鈴木梅太郎の青年時代から晩年までを、加藤剛・頼の親子で演じる。劇的昂揚はやや弱いが、好感度は高く、静かな余韻もいい。彼を支える妻役の有馬理恵が、気丈で明るい持ち味を出して好演した。
ミュージカル泣かないで(音楽座)
遠藤周作の旧作をよくぞここまで巧みにミュージカル化したと感心。ハンセン病患者に尽くす「決意」が、やはり感動的。
*****************************************************************************************************************
 こんにゃく座『オペラ ネズミの涙』2013.11.26発行
こんにゃく座『オペラ ネズミの涙』2013.11.26発行
やはり希少でユニーク、実力ある和製オペラ創造劇団だ。 去年だったか、カフカの『変身』を観て以来の観劇だった。
観るたびに、その歌唱や演奏など「音楽力」のレベルの高さに感心する。
今回の舞台は、一幕こそテンポに緩慢さを覚えたものの、二幕に入るや俄然盛り上がった。
劇的なストーリー性と現代的なテーマ性が魅力で、例会候補にふさわしい上質のオペラといえよう。
主筋は、戦火をくぐり旅芝居を続けるネズミ一家を襲う悲劇。
「戦争」のせいで息子と娘を亡くすのだが、悲しみと怒りの「涙」を流した後もめげず挫けず、天竺(ユートピア)を目指して新たな旅立ちをするネズミたちの姿は、感動的でさえある。
「ネズミ=庶民」という分かりやすい寓意性。 いつの時代も、戦争は、まず弱者を痛めつけるのだ。
「強い者が少し我慢すれば弱者が救われるのに…」という腹から絞り出すような台詞が強く印象に残る。 まさに、今の日本や世界の縮図ではないか。
シリアスな題材ではあるが、カネ・太鼓の朝鮮音楽?が明るさ、軽やかさ、そして猥雑な雰囲気を醸し出す。
頻出する若者向けのギャグや「流行語」には賛否があっても、京劇スタイルの劇中劇「西遊記」もけっこう楽しませてくれる。
終幕が特に鮮烈なのは、かつて俳優座で観た『肝っ玉おっ母とその子供たち』がモチーフになっていたからだ。
軍隊の急襲を村に知らせるために太鼓を打ち続けて射殺される娘の話は、ブレヒトの古典的名作そのまま。
定評ある劇作家・鄭 義信(チョン・ウイシン)の手腕、その見事な換骨奪胎ぶりが、成功作を生み出した第一の要因だろう。(三宅 修)
*****************************************************************************************************************
 こまつ座『うかうか三十、ちょろちょろ四十』2013.07.17発行
こまつ座『うかうか三十、ちょろちょろ四十』2013.07.17発行
劇団東演の『ハムレット』は3時間越えの大傑作だが、「珠玉」と呼ぶにふさわしい短篇舞台も多い。
もう山本安英の『夕鶴』や鈴木光枝『おりき』は伝説となり、『釈迦内棺唄』も語り草。
近いところでは、『月光の夏』『父と暮らせば』が大きな感動を残した。
そして、上演時間がたった1時間15分のこの新作も、例会になれば「記憶の殿堂入り」は間違いない。
どこか懐かしい響きのわらべ歌で幕が開き、立体絵本のような心なごむセットが目に飛び込むと、一気に「民話の世界」が広がった。
歌でもヤユされる「バカ殿様」が、賢くて美しい村娘に恋をし、見事に振られ、心の病になる…。
その9年後。 娘は村一番の大工と結婚し、一女をもうけているが幸せそうでない。
「重い病い」で働けなくなった彼が、心もすさみ、女房や娘に辛く当たるからだ。
そこへ自分が医者だと思い込んでる殿様が訪れ、「病気はもう治っている」と断言。 それを信じた大工と女房は幸福感に包まれ…。
そして、また9年後。 病が治った殿様に、成人した娘から悲しい後日談が明かされる。
あの「診たて」の後、無理働きをした父と母が「ニセ医者」の真相を知り、急死した、って。
ショックを受けた殿様の、我が半生を振り返り慨嘆する言葉が、この劇のタイトルだ。
井上ひさし24歳時の処女戯曲といえど、やはり「社会派」の片りんを見せる。
権力(殿様)が振りまく「幻想」を信じた庶民(大工と妻)の悲劇、という「現代性」を感じさせたのだ。
遊び心に溢れる舞台と裏腹の、「ホントは怖い井上民話」の趣き…。
舞台転換時の雷鳴や、開幕と終幕に流れる不気味な重低音は、「無常感」を増幅し、あの震災や原発事故さえも想起させた。
才気煥発な鵜山仁演出は、今回も僕好みだった。
******************************************************************************************************************
エイコーン『メアリー・スチュアート』 2013.05.13発行
 まだ統一国家としての「大英帝国」が成立していない18世紀のイギリスに、甲乙つけがたいカリスマ的魅力を持った二人の女王がいた。
まだ統一国家としての「大英帝国」が成立していない18世紀のイギリスに、甲乙つけがたいカリスマ的魅力を持った二人の女王がいた。
北部・スコットランドのメアリー(栗原小巻)と、南部・イングランドのエリザベス(樫山文枝)。
その凄まじい対立と葛藤を描いた、このシラーの古典的名作は、いまなお観る者を強く惹きつける。
粗暴な夫を殺したメアリーは、従姉妹エリザベスのもとへ逃れ庇護を求めるが幽閉されてしまう。
舞台は、その19年後にエリザベス暗殺を企図したとして「死刑判決」を受ける日から、
メアリーに想いを寄せる伯爵の計らいで実現した両女王の「対面」の日、
そして命令系統の手違いによる「死刑執行」の日までを、緊迫感いっぱいに描いている。
壮大な歴史劇を、たった「三日間」に凝縮・収れんすることで、濃密な人間ドラマの味わいが深まったのだ。
劇的な三日間の中でも、互いに愛憎や畏敬の念を持ちつつ、ついに対面する日の、えも言われぬ空気がたまらない。
恭順や命乞いを拒否するメアリー、冷徹な権力者を演じ続けるエリザベス。
為すすべもなく、数奇な運命に翻弄されていく二人の「孤高」の哀しみが、胸を打つ。
小巻・樫山の両ベテラン女優の「競演」は、やはり、「気品と誇り高き美しさ」を体現して見応えがあった。
実力本位の多彩な配役に隙はなく、簡潔さとテンポを重視した脚色・演出(加来英冶)も高く評価されてよい。
後日談だが、「英国と結婚」して生涯独身を通したエリザベス一世は、その後継者に、メアリーの息子を選び、その血筋が今の英国王室につながっているという。
これからも、その種のイギリス映画を見るたびに、僕はきっとメアリーを思い起こすことだろう。
彼女は、死して「伝説」となった。(三宅)
******************************************************************************************************************
関西芸術座『歓喜の歌』
将来の例会づくりの参考にするべく東京中心に研究観劇を続けており、昨年もまた20劇団あまりの40数本を観た。
その中でも、大阪屈指の老舗劇団によるこの新作は、僕の昨年度ベスト5に入るだろう。
NHK「ためしてガッテン」の司会で知られる立川志の輔の創作落語を見事に換骨奪胎し、上々の舞台を創りあげた。
自前ビルを手放しての貸劇場による再出発第一弾は、劇団員の強い心意気とエネルギーを結集して成功した。
二つの女性コーラスグループの大晦日公演が、公民館主任のミスで日程が重なる。 さあ大変、ダブルブッキングってやつだ。
うまく解決せねば、彼と幼馴染の新市長によって、公務員攻撃とリストラの格好の餌食にされるのは必定。
テンヤワンヤの顛末を描く喜劇は、笑いと感動の渦を起こして終幕まで弾み続けた。
この女性市長が某大阪市長の言動とそっくりで、「ハシズム」という言葉には思わず拍手、爆笑。
一方、パートの合間に時間を捻出し、夫の介護などの困難にもめげず、生き生きと「サークル活動」を続ける女性たちは、みんな健気で逞しい。
有りそうでなかなか無い「身近で楽しくて元気の出る芝居」って、いいもんだ。
主役の公民館主任(福寿淳)はじめ中堅・若手の奮闘に好感を覚えた。微笑ましいベテラン三女優の共演もいいスパイスになった。
しかし最大の功績は、「志の輔」落語の面白さを増幅した脚色(駒来愼)とテンポのいい演出(門田裕)にあるだろう。
原作と映画を超えるほどの稀有な傑作、といっても誉めすぎにはなるまい。 これは、ぜひとも四国市民劇場の例会にすべきだ。
******************************************************************************************************************
日韓演劇フェスティバル『トンマッコルへようこそ』2012.03.26発行
演劇と同じほど大の映画好きなので、もちろん、数年前にこの韓国映画は見ていた。
その感動作のオリジナルは実は舞台だと聞き、大いなる関心を持って大阪へ駆けつけた。
僕としては初見の、劇団「桟敷童子」製作。
1950年、朝鮮戦争の最中とはいえ、銃声も届かない山深い小さな村。
そこで偶然が重なって、米兵パイロットと南北朝鮮の兵士たちが出会う。
始めは殺意や敵対心が露だったものの、
牧歌的で平和な村の空気に癒され、農作業を手伝ったりしてるうちに、兄弟のような友情が生まれる。
しかし彼らは、ついに来る爆撃から村と村民を守るために死んでいくのだった。
黒沢映画『七人の侍』を髣髴とさせる終幕だ。
父親が写っている一枚の集合写真のいきさつを、現代の作家が探っていく構成もよく、巧みに観客を引っ張った。
願わくば、早口が多い台詞に緩急のメリハリがもっとほしいし、視覚的な美しさに更なる工夫がほしいものの、
二度のカーテンコールに驚き照れながら手を振る出演者たちは、とても好感が持てた。
多少評価が割れようとも、希少で見事な反戦劇であることは間違いない。
そうそう、トンマッコルとは、「子どものような純真さ」を意味するそうだ。 いい響きだなあ。(三宅)
******************************************************************************************************************
 テアトル・エコー『アラカン!』2012.01.17発行
テアトル・エコー『アラカン!』2012.01.17発行
全国各地で「高齢者劇団」が話題を集めている。
蜷川幸雄さんの興した埼玉のそれをはじめ、徳島でも浅香寿穂さん主宰の「劇塾マダーラ」が意気軒昂たる活動を続けている。
いずこも中心メンバーは、アラカンことアラウンド還暦(60歳前後)。
「鞍馬天狗」の嵐寛寿郎を知る最後の世代でもある。
この舞台は、そんなシニア男女がシニセ劇団でシェイクスピアの『オセロー』上演に挑む、といった新作喜劇だ。
劇団経営の一助とすべく開設されたシニア俳優養成所。
そこに集まったアラカンたちの、涙ぐましい奮闘努力が可笑しくてたまらない。
「笑いが笑いを生む」とでも言おうか、市民劇場の例会になりうる「喜劇」で、こんな哄笑が続くのは珍しい。
そして、決めるところはちゃんと決めるのだからたまらない。
熟年・素人俳優の創意工夫?で「オセロー」は奇妙なミュージカルに変わっていくのだが、
そんなドタバタに翻弄されながらも、劇団と役者の「魂と矜持」を強く感じさせる台詞が腑に落ち、結末が爽快。
「プロの老舗劇団」エコーの面目躍如、といったところか。 (三宅)
******************************************************************************************************************
文化座『獅子』2011.12.02発行
 ちょっと前に見た東京演劇アンサンブル『山脈』で、自立する女性の凛然とした姿に新鮮な感動を覚えた。
ちょっと前に見た東京演劇アンサンブル『山脈』で、自立する女性の凛然とした姿に新鮮な感動を覚えた。
そういう古典的?名作に、劇団も観客も時々きちんと向かいあうべきだろう。
今回の、好感の持てる丁寧な舞台に出合って、ますますその思いを深くした。
意に染まぬ結婚を迫られた娘が、相手の仲人を迎えた日に、愛する人を追って「満州」へ発つという
単純なストーリーながら、戦争真っ只中という「その時代」を思えば、彼女の「決断」に誰もが深い感銘を受けるのだ。
娘の乗った列車が家の近くを通り過ぎる時、「獅子舞」の名手であった父親が、
酔っ払いながらも、はなむけのために舞い踊るラストシーンでは、切々とした親の愛が強く胸を打った。
ただ、若いカップルに幸多かれと願いつつも、現代の観客である僕達は、知っているのだ。
その二年後には過酷な敗戦と苦難の引き揚げが待っていることを…。
終演後、僕は以前に青年座で観た『明日』を思い出していた。 原爆前日の長崎を描いていたからだ。
舞台に感情移入して楽しみ、歴史は客観的に見つめる、それが僕の鑑賞スタイルかもしれない。 (三宅)
******************************************************************************************************************
俳優座『妻の家族』2011.09.06発行
 たとえ血縁でなくても「絆」や「家族」は作れる、舞台からはそんなメッセージが強く伝わり、心優しい余韻を残した。
たとえ血縁でなくても「絆」や「家族」は作れる、舞台からはそんなメッセージが強く伝わり、心優しい余韻を残した。
2人の元夫と6人の子供たちのもとへ、「ハハキトク」というメールが届く。 発信人は、そのハハ。
さっそく末娘夫婦も駆けつけるのだが、その新婚間もない夫は、妻と奇妙な「家族」に振り回され続ける。
二幕の葬儀シーンから大いに弾み、てっきり母のかと思いきや、同居していた息子が旅先で雷に打たれたものと分かり爆笑。
その彼も実は生きており、突然の帰宅で爆笑。 真水を張った庭の池に何人もが落ち込み爆笑。
ありえないような展開が楽しい。
結局、先の夫が「困った面々」の借金苦を救い、一緒に住み始めることで大団円。
「新劇」とは無縁の?若い作家と演出家で、奇をてらった舞台になるかとの予想に反し、斬新だがこてこての「人情喜劇」。
若手もベテランも楽しそうに「参画」している雰囲気が、とても気持ちよかった。(三宅)
******************************************************************************************************************
俳優座『月光の海 ギタラ』2011.07.20発行
 「珠玉」とは、こういうのを言う。
「珠玉」とは、こういうのを言う。
派手な大作ではないが忘れられない輝きを放つ、好感の持てる舞台であった。
自ら企画・出演した加藤剛の、誠実で真摯な人柄がにじみ出て、平和を希求する変わらぬ熱情がほとばしった。
かつて深い感動を残した劇団東演の『月光の夏』を思い起こすが、その「名作」の二番煎じになるのをも恐れず、
まなじりを決して取り組み、衒いのない優れた舞台を生み出したことに、僕は共感の拍手を送る。
現代の沖縄の孤島。
その崖(ギタラ)に立つ老紳士、彼は元特攻隊員で、「体当たり」に失敗し帰還した辛い過去を持つ。
言語に絶する苦悩が、激戦時の悲惨な光景と共によみがえり、観客の胸を打って止まない。
回想場面での若い彼を実息の頼三四郎が演じ、「時のつながり」を感じさせるのがいい。
生演奏もいい。 二人のギタリストが奏でる清冽な音楽が、もう一つの主役になっているのだ。
こういう秀作が東京公演のみというのでは惜しすぎる。(三宅)
******************************************************************************************************************
劇団東演『ハムレット』 2011.05.24発行
 3月の観劇上京は大地震ぼっ発の日だった。
3月の観劇上京は大地震ぼっ発の日だった。
一番観たかった俳優座劇場の『わが町』などが中止になり、辛うじて観劇できたのはこの一本だけで、まさに奮闘公演。
主役に抜擢された南保大樹はじめ、徳島でも『長江』『月光の夏』で馴染みの俳優陣が熱演した。
いまやロシア演劇界に確かな地歩を占めたベリャコーヴィッチの演出は、相変わらず歯切れよく快感を覚える。
俳優でもある彼が、自ら叔父役を貫禄十分に演じるなど、前回の『どん底』同様、3人のロシア人俳優の共演も楽しい。
彼らのロシア語のままの台詞は詩的な響きがあり、醸し出す日露融合の趣きは、この劇団の独壇場といっていい。
僕らが見慣れているBGMの少ない「新劇」とは異なり、音楽と照明を多用する技は健在だ。
簡にして要を得たセットも僕好み。
それらすべてが、今回の舞台の成果を生んだわけだが、何よりも、原作の名場面・名台詞を巧みに網羅したことをまず挙げねば、と思った。
沙翁もにっこり、ってとこか。
******************************************************************************************************************
演劇集団
円『シーンズ・フロム・ザ・ビッグ・ピクチュアー』2011.03.25発行
 この後も演劇倶楽部「座」の詠み芝居『五重塔』など多数の秀作に出合ったが、
この後も演劇倶楽部「座」の詠み芝居『五重塔』など多数の秀作に出合ったが、
やはり半年前のこの舞台は記録と記憶に留めておきたいと思う。
北アイルランドと思える「架空の街」で様々な事件が起きる。
食肉工場・雑貨店・酒場・野外など数十の場面(シーンズ)が描かれるのだが、それらがバラバラのようでいて、
いつのまにか全てが連関し、全体が一枚の「大きな絵」であるかのように見えてくるのが面白い。
内容は、いたって現代的で、今日の日本の状況とも重なる。
就職難にあえぐ若者、はびこる犯罪、破綻する夫婦、広がる社会不安…。
それらに少なからぬ嫌悪感を覚えつつ、しかし観客はそれでもなお、日常の「過ぎ去っていく時間」の貴重さを痛切に思うのだ。
まさに、名作『わが町』現代版の趣き。
終幕の、孤独な老人が流星群を仰ぎつつ亡妻の名を呼び「寂しいよ〜」と叫ぶ姿は、鮮烈で秀逸だった。
******************************************************************************************************************
 俳優座『樫の木坂四姉妹』2011.01.25発行
俳優座『樫の木坂四姉妹』2011.01.25発行
どんどん舞台に引き込まれながら、「入魂」という言葉が脳裏にずっと浮かんでいた。
制作と、作家、演出、俳優ら創り手の「魂」を強く感じさせる、渾身の舞台であった。
長崎原爆でも息絶えなかった巨木のごとく、
苦難の戦後をしぶとく生き抜いてきた老女三姉妹の日常を、カメラマンとの交流をまじえ、「明るく」描いている。
そこへ時折、65年前の光景(双子だった三女のピアノ、幸せな家族団らん)を挿入する。
この鮮やかな対比が、原爆の罪悪と悲劇性、それを伝え続ける大切さをいっそう鮮明にさせるのだ。
長女が、被爆の語り部として修学旅行生に話しかける懸命な姿は、観客の胸をも打つ。
その大塚道子はじめ、岩崎加根子・川口敦子という個性的な超ベテラン女優の初の?共演・競演は、けだし見もの。
こういう秀作は、全国津々浦々まで巡演するだけの価値があるが、まず、鑑賞会が例会にしなくっちゃ。
******************************************************************************************************************
前進座『さんしょう太夫』
 素晴らしい舞台は鮮烈に心に残る。
素晴らしい舞台は鮮烈に心に残る。
6月に和歌山演劇鑑賞会で観させてもらった『さんしょう太夫』もその一つ。
30年前に例会になって以来の再会だった。 そしてやはり、その感動と余韻は格別のものだった。
仏法僧の集団が読経しながら客席から登場する荘厳な幕開きがいい。
舞台に溶け込むような黒装束。 彼らにかぶせて舞台一面に仏典が映写される。
それが斬新な白黒模様となり摩訶不思議な効果をあげ、独特の劇世界に観客を一気に引き込むのだ。
装束を取った彼らが、「安寿と厨子王」はじめ何役かずつを熱演し、また舞台両端で和楽器を演奏する。
歌い手、語り部も巧みにこなしていく。
その優れた音楽性で「和製ミュージカル」と言えなくもないが、そうあっさりとは括れないような、荘重さや格式を感じさせる。
物語そのものは、中高年世代なら誰もが子どもの頃から慣れ親しんできたもので、
やはり幼い姉弟の悲劇に胸を締め付けられるだろう。
人買いによる母との離別、山や海での苦役、焼きゴテ、安寿の死、
厨子王の栄達、山椒太夫の処刑、盲目の母との再会がドラマティックに展開し、
「説教節」特有の中世的な身代わり信仰や勧善懲悪というテーマが、役者と演出の力で際立つ。
無駄をそぎ落とした見事な舞台は、能狂言の様式美や「素劇」の手法を思わせた。
何拍子もそろった傑作だけに、なるべく早く例会にしたい。