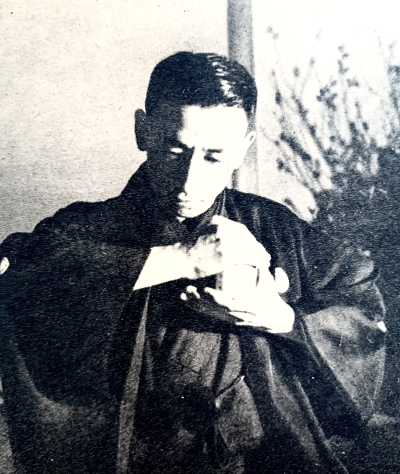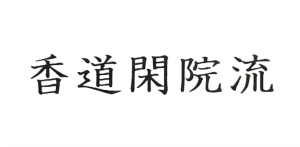
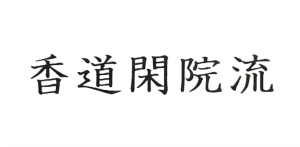
聞香文化は江戸時代には隆盛を極め、諸派の輩出と共に家元制度が確立されます。
享保年間、諸派の一つとして香道閑院流が創起されました。当時、香問屋で聞香に長けていた初代当主が閑院宮家より出入りが許され、やがて香事を預かる様になった事に始まると伝えられています。
明治時代,文明開化による文化の衰退,戦時下の空襲による家屋の消失などを経て第九代(1989年没)が戦後復興の中で関西の文化人達と親交を図りながら当家の再起に取り組みました。もちろん
”お香” はかおりを鑑賞するものであります。”香道” は自然界からの奇跡の恵み ”沈香”と向き合い,邪念を祓い香気一点に集中します。やがて無の境地へ達する事が究極そされています。そのために”道”
という心身の鍛錬を課した強い精神性を求め成立しています。
閑院流では「香道は一木の精粋を究めることが何より大切である」そして「組香(香席)は聞き当てる場ではなく師匠からの面授口訣と教養の場である」と説いています。




大正時代の聞香