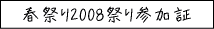
番外編:幽霊対妖精
浅間良夜は超常現象の類を全て否定している、と言うわけではない。ただの一度もそれらしい物を見たことがなく、心霊スポットと呼ばれる場所にまで出掛けた時すら、何も見付けることもなく帰ってきたし、信じてしまえるほどの説得力を感じる話も聞いたことがない。それでも心霊番組とかがあれば見てしまう方で、怪談や幽霊の話も嫌いではない。
だから、幽霊を初めとしたオカルト、超常現象のたぐいに対して『あれば面白いけど、多分ないんだろう』と、まあ、一般的な考え方で接して生きてきた。
だがしかし!
「……何よ?」
テーブルの上に立つ全高十七センチの影、彼女はアイスコーヒーのグラスから顔を上げると良夜の顔を不機嫌そうな表情で見上げた。頭を動かすたびに流れ落ちる長く美しい金髪、その身を飾るのはフリルたっぷりの白いゴスロリ調ドレス、そして背中にはトンボのような羽、彼女、アルトは妖精さんを自称していた。
「うるさい、喋る超常現象」
彼女の姿を見ることが出来るのは、彼ただ一人。事情を知らない第三者が見れば、彼がグラスに向かって楽しそうに会話をしているようにしか見えないだろう。事情を知っているのは、昔は良夜と同様にアルトの姿を見ることが出来た老店長と、彼にアルトの話を聞いて育ったその孫娘の二人だけ。
「愛らしい妖精さんの姿に魅入ってたの? 存分に見なさい」
彼にしか見えない妖精さんはグラスの中からマイストローを引き抜き小さくタメを作った。そして雫を払うかのようにそれを一閃、良夜の顔へと突きだし「このロリコン!」と真顔で断定した。
「俺はロリじゃない!」
誰気兼ねく彼女と語らえるよう、老店長が用意してくれたのは窓際端っこの目立たない席、彼らはいつもここで誰も観賞してくれない漫才を繰り広げていた。アルトが大好きなコーヒーと大きな窓から見える山の景色をお供にして……
ここは喫茶アルト、妖精アルトの住まうアンティーク喫茶店。
「それで? 私の顔を見て、何を考えていたわけ? 欲情してたって言うんなら、ポーズを作ってあげるわよ」
そう言うと、アルトはテーブルの上に立ち、ノースリーブドレスの裾をちょこんと持って、お辞儀をして見せた。いわゆる、淑女風のお辞儀って奴だ。
「俺の守備範囲は百五十センチ以上なんだよ」
「だから、十五センチに負けなさいって……じゃぁなんなの?」
摘んだドレスを僅かに持ち上げ、見る? と首をひねる。もちろん、答えはノー。イエスと答えた日にはなんと言って罵倒されるか判った物ではない。良夜の答えに無理しちゃってっとアルトは返すと、ドレスの裾を手で払ってテーブルの上に腰を下ろした。
「まあ、なんだ……妖精が居るんなら、幽霊もいるのかな……って思ってたんだよ」
アルトが座り終えるのを待つと、良夜は一瞬の逡巡の後に決心を付けて切り出した。
「幽霊なんて居るわけないわ」
即答。彼女は一辺の迷いもなくきっぱりと言い切った。
「……何で?」
「だって、会ったことないもの」
がくっと良夜の全身から力が抜けた。
彼女の言葉に一片たりとて迷いは見えないが、妖精だって大多数の人間はあったことがないから居るわけがない、と言うに決まっている。
「素晴らしく科学的な答えだな……」
「そうね、良夜よりかは頭いいわよ、理系も文系も」
「ちっ……」
事実である上に、前期の定期試験で力一杯お世話にもなった。良夜はその言葉に反論が出来ず、苦虫をかみつぶしたような顔で舌を鳴らした。
「で、どうしたの? 幽霊の知り合いでも出来た?」
口喧嘩に勝利を収め、アルトは薄っぺらな胸を誇らしげに反らす。良夜はそこから視線を逸らして、緑を湛える山と渓谷、そして糞暑い太陽へと向けた。ほとんど毎日眺めている見慣れた風景がそこにはあった。
「俺のバイトしてるところ……出るんだよ」
工学部の学生として、良夜はこんな台詞を吐くことは甚だしく不本意。だから、視線を逸らしたまま、まるで独り言でも言うかのように呟いた。
「良夜のバイト先って、スーパーよね? お総菜の美味しい……そこに? 幽霊が?」
アルトはキョトンとした表情、口にこそ出さないが『まさか、馬鹿馬鹿しい』という感情を隠しもしない。しかし、『まさか、馬鹿馬鹿しい』というのなら、喫茶店に妖精が常駐していることこそ、正に『まさか、馬鹿馬鹿しい』話だ。その辺の彼女は理解しているだろうか、と良夜は少し不安になってくる。
「そうだよ」
良夜はそう答え、まるで人目を忍ぶかのように、体をテーブルの上へと乗りだし小さな声で事のあらましを説明し始めた。
良夜がスーパーで仕事を始めたのは、大学生活にも慣れ始めたゴールデンウィーク終了直後のことだった。大学へ通学環境と自然環境にだけは恵まれた――平たく言うとド田舎――彼のアパート、そこからスクーターで一時間もかかる町中のスーパー、それが彼のバイト先だ。
良夜が配属されたのは通称『ドライ』と呼ばれる部門だった。扱う商品はインスタント食品や調味料、米、缶詰、そして『ドライ』なのに『ウェット』百パーセントなジュースや水までもがここで扱われる。その理由はイマイチ不明、昔からの伝統。
事件は、彼がここで働き始め、二週間ほど経った頃に起こった。一緒に働くパートのおばさんが「とあるレーンに居ると肩が重くなる」と言いだした。当初は誰もがただの肩こりだと思った。ドライが扱う商品には米や砂糖、塩と言った重い物もある。肩こり腰痛なんかは職業病のような物、気にしていては始まらない。
しかし、それはそのレーンにいるときだけ発病し、そこから離れるとすっと軽くなると言う。当初、彼女を含め誰もが、それをただの気のせいだと思っていた。しかし、他人、良夜にまで伝染し始めたのだから、さあ、大変。誰もがそこの場所にいるときだけ肩が重くなり、そこから離れるとすっと軽くなるという現象に頭を痛めるように……いや、肩を落とすようになった。
そう言うわけで、そこでの仕事を誰もが嫌がるようになるのも時間の問題だった。しかし、嫌がったところで、誰かがやらないければ仕事はいつまで経っても片付かない。誰かがやるしかない。そして、その『誰か』には一番の下っ端がなると、相場は決まっている。
ここでの一番の下っ端というと、バイトの中で一番新しい人、すなわち五月から働き始めたばかりの良夜だ。これが世の中の仕組み、世間で上手に生きていきたければ、そう言うことは受け入れざるを得ない。
いやだなぁ、肩が重いなぁ、と思いながら働き続けて数日が過ぎたある日のこと。一人の客が塩の袋を落として破った。これ自体はよくある話。手の空いている奴が掃除をして、後の話は店長なり主任なり、居なければ正社員の誰かに押し付ければいい。弁償させるか損品扱いにするかは、彼らが決めることで、下っ端バイトにその権限はないのだから。
問題は、そこが現場が心霊スポットで、手の空いてそうな人間が良夜しか居ないって事だけだ。良夜にとって、特に後者は大きすぎる問題だと言っても良い。ただでさえ、居るのが嫌な場所、そこでの仕事を増やしてくれたお客様に、心の中で毒を吐きながら良夜は、モップで散らばった塩の粒を履き取り始めた。
嫌だなぁ、肩が重く……あれ? どういう事だろう? 肩が全く重たくならない。まるで、美人マネージャーにマッサージでもして貰ったみたいだ。実際にして貰ったことないけど……
今までの肩の重さは、気のせいだったのかだろうか? 何度首をひねったところで、良夜一人で判る話ではない。判らないから、相談してみた。
仕事が終わり、閉店作業も一通り終わった後、良夜はその現象を知る人々をその場所へと集めた。すると、他の人も『今はならない』と言うのだ。しかも翌日も翌々日になってもその現象が、そこで起こることはなくなった。
再び店員達が集まり、閉店後の会議が行われた。そこでの結論は――
「『は・か・たの塩!』でもお清めは出来るンだなぁ……と」
例のCMのようなアクセントを付けてみる。
それまで、まじめくさった顔で話を聞いていたアルトは、聞いて損したとでも言うかのようにペタンとテーブルの上へと両足を投げ出した。短めのスカートから伸びるのは白いガーターベルト付きストッキングに包まれた華奢な足、アルトはストローを上下に振りながら、良夜の顔を見上げて『馬鹿?』と呟いた。あぁ……『?』付いてなかったかも……
「だってよ、その証拠ってのもあれだけどさ……今度はその現象が隣のレーンで起こり始めたんだよ」
良夜自身、間抜けな話だと言うことは重々承知している。アルトが呆れた顔をしてみせると、良夜も乗り出していた体を背もたれへと押し付け、体裁が悪そうに伸びた前髪を指先に絡めた。少し長くなった髪、高校時代と違って頭髪検査もないもんだから、ついつい、散髪屋が縁遠くなってしまうな、と余り関係のないことを考えながら……
「じゃぁ、何? そこにはやっぱり幽霊が居て、お塩でお清めされた所が嫌になって他の場所に逃げた、って事?」
「そうそう、そうとしか考えられないだろう?」
「……じゃぁ、他の場所もお塩で清めなさいよ」
「してるよ。今、店内では塩を撒くのがちょっとしたブームなんだ」
自分の担当箇所にその幽霊がやってきたことに気付く――急に肩が重くなる――と、そこの担当は慌てず騒がずこっそり塩をひとつまみ撒く。塩を撒かれると幽霊は別の場所へと移動する。そして、また、その移動先で塩が撒かれる。今、幽霊さんは塩を撒かれながら、店内をぐるぐる回っているのだ。
「幽霊はその場に塩を撒かれると、一週間以上塩が撒かれない一番近い場所へと移動する。この事実から塩の有効期限は一週間だと統計上の結論が出た」
「……調べたの?」
「ちょっとな……こっちにおハチが回ってこないように」
アルトの呆れ具合が更に加速していくのが、良夜にも良く判る。まあ、自分でも馬鹿なことをやったなぁという自覚はある。しかし、こういう事でもやってないと恐くて働けなくなりそうだったのだ……
「……幽霊も馬鹿なら店員もかなりの馬鹿ね……そして、馬鹿の親玉」
上下に振り続けられていたストローが良夜を指す角度にピシッと止まる。
「指すな……」
そのストローを良夜が指先で弾くと、アルトは良夜の指先を剣先に見立てペチペチとチャンバラを始めた。
「夏休みの自由研究として、提出、してみなさい。きっとウケるわ……よっ! と」
「統計学、今期とってない、からな……っと、イテッ、刺すな!」
数度の切り結びの果てに、良夜の爪と肉の間に細いストローが突き刺さる。
それを抱え込んで涙を流す良夜と、勝ち誇った笑顔を浮かべて切っ先をペーパーナプキンで拭くアルト……片方は武器で片方は素手なんだから、刺すのは反則ではないのだろうか……
「早稲田に編入してOH槻教授の研究室に入るとか……ごめん、偏差値が違いすぎるわね」
「……お前、今、ここの常連客、全員を敵に回したぞ」
少なくとも、俺にとっては完璧に敵だ……痛む指先を抱えたまま、辻斬り浪人よろしく切っ先を拭くアルトを見て、良夜はそう確信した……
さて、それから三日ほどが過ぎ、良夜のバイトが休みの日。常に暇と好奇心をもてあましているアルトは、その心霊スポットへの案内を要求してきた。面倒くさい事この上ない話だが、飯を食べに行くたび連れて行けと言われるのももっと面倒くさい。一度連れて行って、大したことがなければこいつも満足するだろう、との判断の元、良夜はアルトを連れて休みだというのに街中のスーパーへとやってきた。まあ……それ以外にも、幽霊と妖精、もしかしたら……との期待も何処かにあった。
スーパーまではスクーターで小一時間、バブル直前に計画され、崩壊後は半ば放棄されていた埋め立て地区。そこは何年か前から再開発地区に指定され、県外企業の誘致が盛んに行われている。その誘致に乗った大きめのスーパー、それが良夜のアルバイト先。時給が良い事と売れ残りのお総菜を安く別けてくれるのは、裕福とは言えない大学生にはありがたい。
良夜はアルトを頭に乗せた姿で、使い慣れた従業員用駐輪場ではなく、入り口傍の一般客用駐輪場から店内へと入っていった。
平日だというのに随分な賑わいを見せる店内、そこで働く人々に良夜の知り合いは少ない。彼が夕方から閉店までの時間で働いているのに対し、今がほぼ朝一番という時間だからだ。朝なら幽霊も活動が弱まっているかも知れない、と言う安易な考えから、この時間帯を選んだ。
キョロキョロと店内を見渡し見知った顔を見付けると、良夜はアルトを頭に乗せたままそこへと駆け寄った。大きく上下に揺れる頭、アルトが酔うと文句を言っているがとりあえず無視する。
「おはようございます、主任」
主任と呼ばれた男は、年の頃なら三十半ば、少し小柄で僅かに垂れた目元が気の弱さと人の良さを物語っている。
「あれ、浅間くん、どうした?」
彼は良夜に声を掛けられると、忙しく動いていた手を止め彼の方へと体を向けた。仕事以外にほとんど店を訪れる事のないバイト学生の登場に驚いた様子を隠しもしない。遠いからな……ここ。
「売り出しなんで、買い物に……それで、あの……アレ、何処にいます?」
『あの』の後に続く言葉は小さく抑えられた物になっている。客商売の店で『幽霊が居る』なんて噂になったらおおごとだからだ。
「愛店精神に目覚めた? アレというと……コレ?」
それまで普通に話していた彼の言葉も、良夜に連れるように押さえられ、二人は顔をつきあわせるような格好で話し始めた。
「そう、コレ……」
まずは店長が、続いて良夜が、自分の胸元で両手の指先を下に向けた。いわゆる、ジャパニーズスタンダード幽霊の仕草。
「さっき、パンの山崎くんがお塩を捜してたから、多分、その辺じゃないかな……」
良夜がありがとうございましたと言うと、仕事休みだというのに君も暇だね、と主任は苦笑いで付け加えると、止めていた手を再び仕事へと戻していった。
「パン担当の山崎って……名前で決めたのかしらね?」
「アホなことを言うな……パンの人が塩で追い払ってたら、諦めろよ」
パンの売り場は良夜が担当しているドライの売り場から近い。毎日歩く慣れた通路を、良夜は人の波をかき分けるように進んでいった。
「次の場所は判らないの?」
「流石にな……候補地が多いし……」
大体、ここ一週間、何処で塩を撒かれたか、と言う事まで事細かく調べているわけでもない。誰かがあの現象で所在を確認しない限り、幽霊が何処にいるかを知る術はない。
「そう……じゃぁ、諦めるわ……ここ、よね?」
そしてついにパン売り場へと到着……食パン、あんパン、カレーパン、様々なパンが並ぶ一画。多くの客が行き交う場所だが、その客の中に幽霊がいるかも知れないと言うことを知る者はほとんど居ない。
「すぐには反応が出ないからな。十分くらい立ち止まってるんだ……」
すぐに反応が出れば、客も気がつく。十分、十五分と立ち止まっているうちにじわじわと肩がだるく、そして重たくなっていくというのが、この店の心霊現象。幽霊も気を使っているのかも知れない。もしかしたら、客にまで手を出せば、本格的にお祓いされてしまう可能性を考慮に入れているのかもしれない。だとしたら、知能犯な幽霊だ。
良夜は意を決し、パンの棚へと近付く。もし、パンコーナーにいるのならば、この辺りで怪現象は起こるはず……正直、恐怖に彩られた緊張感を味わっていることを否定できない。
「暇ね、パンは買わないの?」
「あっ……あぁ、パンはアルトで昼に食ってるからな……」
「でもボーッと立ってたら、変に思われるわ」
それに引き替え、アルトはいつも通り。口は減らないし、お上りさんよろしく、回りを見渡し落ち着かない様子を見せている。
「そう思うんなら、余り話しかけるなよ」
「……判ったわ」
ただ、肩が重たくなるのを待つ十分、と言うのはなかなか堪える。何より、心霊スポットでいつもの掛け合い漫才をやる気にもなれない。良夜が黙り込めば、珍しくアルトも黙り込む。
良夜は買う気のない食パンを手にとっては、棚に返すと言うことを何回も繰り返し、その瞬間を静かに待ち続けた。
「何よ……心霊現象なん――あれ……」
五分ほどが過ぎた。早くもアルトは飽き始め、良夜の髪を引っ張って不満の意を表そうとした。そして、その言葉が不意に止まる。
「どうした?」と良夜が視線を上へと向ける。頭の上に座っている物だから、見えるのは額の方にまで伸びた足と、その先端を覆う素朴な木靴だけ、彼女の表情を見ることはちょっと出来ない。
「肩が重い……かも知れないわ」
独り言、認めたいような認めたくないような、そんな感じを含んだつぶやきが頭の上から聞こえる。その口調、余裕が少し減っているようだ。
「早いな……チビだからか?」
彼女の身長は十七センチ、子供でも百センチはある人間よりも影響が早く出るのかも知れない。
「知らない! 嘘!? 肩だけじゃなくてなんだか、背中全体が……嫌だわ! 良夜」
せっぱ詰まった声、珍しい……初めてだろうか? 頭の上でアルトの体がバタバタとせわしなく動いているのが判った。
そして、異常を告げてものの十秒も経たないうちに、彼女は良夜の頭を蹴って高いスーパーの天井へと向けて羽を広げた。飛び上がる瞬間に見えた彼女の顔からは、血の気がひいているようにも見えた。
「おっ、おい。飛ぶなよ、迷子に――」
なるぞ……と、告げようとした良夜の視線が、天井から一気に床へと落ちる。その先には床に熱烈な口づけと抱擁をかます妖精さんの姿……手足が小刻みに痙攣しているところを見ると、まだ、生きているようだ。
「……あるとぉ……生きてるか? 慌てて飛び出すからだよ、こう言う時は、慌てず騒がず、別の売り場に行くのが正しいんだぞ?」
経験者は胸を張って偉そうに語る。初めて彼がコレを体験した時、慌てて逃げ出したため、彼はその向こうずねを置いてあった荷物にしたたかにぶつけたのだ。
「クゥ……あぁ……」
うめき声を上げるアルト。もちろん、あこがれの床君に抱きしめられている喜びの声ではない。良夜は、誰かに踏みつけられる前に、と地面へと手を伸ばして、アルトの体を拾い上げた。
「イタタッ……良夜! 体が重たくて飛べない!!!」
拾い上げられ、痛む頭を左右に振ると、彼女は血の気のひいた顔でこう叫んだ。
その時良夜は――
『血の気がひいても鼻血ってちゃんと出るんだな……』
と、別のことに感動を覚えていた。
「要するに小さくて力が弱い分、影響が大きいって事だ」
ここは入り口傍に作られた自販機ステーション。良夜とアルトの二人はそこに備え付けられたベンチに腰を下ろし、心霊体験の反省会を執り行っていた。
「鼻血が出たわ……淑女なのに……」
見事な地面へとダイブを決めたアルト、あの場所から離れてすぐ、飛べるようにはなったが、飛べるようになったところで痛打して吹き出した鼻血は止まることはなかった。おかげさまでアルトの鼻には、便所で調達したトイレットペーパーがねじ込まれ、フガフガという間抜けな呼吸音を響かせていた。淑女と言うよりも、悪戯が過ぎて怪我をした活発な幼児だ。
「やっぱりアレかな……小さいから肩だけじゃなく全身が重くなって、飛べなくなったのかね……」
完全なる他人事口調で、彼は先ほどの現象についての考察を行っていた。色々と疑問点はある。しかし、たった一つ、確かなこともあった。それは、あのシーンは非常に面白かった、と言う事。これについては疑う余地もない。それが彼に多大なる余裕という物を与えていた。それに比べれば、実際に質量や重くなるものなのだろうかとか、飛べなくなる物なのかとか、そんな疑問は小さい小さい。恐いには恐いけど。
「スレンダーでたおやかな妖精さんだから仕方ないのよ……アイタタタ……」
いつもの小生意気な口調も、鼻にトイレットペーパーを突っ込んでいるのでは格好が付かない。彼女は真っ赤に腫らした鼻を痛そうに何度も擦っていた。
「帰って大人しくしろって事だな……大丈夫か?」
「大丈夫、すぐに止まるわ……それより、リベンジよ!」
「あぁ、古い流行語だな……」
「うるさいわね。それより、私はあの幽霊の奴にリベンジを決めるわ!」
彼女は妖精だ。妖精が幽霊ごときに舐められてたまるものですか、これが彼女の言い分だった。ここで逃げたら負け、負け妖精としての人生を歩むことになる。だから、絶対にリベンジするんだ! 彼女の鼻息は荒かった……便所紙で蓋がされてるけど……
「止めとけよ、生きてる人間は死んだ人間にかなわない物なんだぞ……と、誰かが言ってた」
「……どうせ、ゲームか漫画かアニメのキャラでしょ、これだからロリコンは……」
「俺はロリじゃないし、この場合の罵倒はオタクって所だろう……」
ちなみに漫画でもゲームでもアニメでもなく、ライトノベル。
「どっちでも良いわよ! 良夜、それとも恐いの?!」
ピシ! また、ストローが差し出され、良夜の鼻先へと押し付けられる。口調は挑発そのもの、恐くないと言えば速攻でこれからの予定が立ってしまうだろう。だが、良夜にそんな挑発は通用しなかった。ヘタレの自覚、あるしね。
「そりゃ、恐いよ?」
「……あっさり認めないで……」
上げたテンションをサラッと流され、アルトはガックリと細い両肩を落とした。
「俺は一般的大学生なの、超常現象はお前一人で十分。あの幽霊とはバイト中に嫌でも付き合わなきゃいけないし――」
良夜の言葉は全てが語られることはなかった。アルトが鋭いストローを彼のまぶたに押し付けたからだ。
「良夜……私とあの幽霊、どっちが恐いのっ!?」
彼女は完璧にキレていた……
ビタン! ばたん! グシャッ!
パン売り場から僅かに離れたところには、冷凍食品のケースがある。
「キャッ! あっ! 舐めんなぁぁぁぁぁ」
本日は冷凍食品五割引の日、多数のお客さんがその中に手を入れては、お目当ての商品をゲットしていた。
「そうだなぁ……今夜は冷凍食品で作る中華フルコースなんて良いかも……」
餃子にシュウマイ、チャーハンも冷凍の物がある。これにインスタントの中華スープなんかを追加してみて……あっ、野菜が少ないな。
「良夜ッ! ちょっとは助けなさい!!!」
のんきに夕飯のおかずを考えていた良夜に、ボロボロになったアルトの怒鳴り声が叩きつけられた。
「ちっ……」
パン売り場と冷凍食品のケースの間には一本の通路、その通路がどちら側のテリトリーに属するのか? それは店員である良夜にも判らない。しかし少なくとも、冷凍食品のケースを挟めば、もう、そこはパン売り場のテリトリーではないはず。良夜はそう判断し、アルトが幽霊相手に繰り広げる過酷な戦いを見物していた。
「良夜!!」
何度目かの悲鳴と叫び声、これも良夜にしか聞こえては居ない。
そろそろ、見物を止めないと八つ当たりが待っているかな、と良夜は冷凍ケースの向こう側から彼女の戦場へと入っていった。
「……一方的だな……」
そこでの戦いは一方的だった。もちろん、負けているのはアルトの方。
リベンジをかましに、戦場へと帰還した時、アルトはフヨフヨと空中浮遊をしながら、その瞬間がくるのを待っていた。良夜がそれ以上近付きたがらなかったためだ。乗り物が近付いてくれないのだから、彼女は一人で決戦の場へと突き進むしかない。
そして、待つこと五分、あの時と同じようにアルトは真っ逆さまに墜落した。違うのは、なんとか顔面から突っ込むことだけは避けられた点だけ。
叩きつけられたアルトは、立ち上がることは出来ても飛び上がることは出来ない。優雅に空中浮遊を繰り返していた妖精さんも、今では地を這う小さな人でしかない。
渾身の力を込めて飛び上がろうとするアルトだが、その体はほとんど飛び上がることない。まるでサージャントジャンプの練習をしている小学生のようにしか見えない。柳の枝に飛び乗ろうとしている蛙……かも?
この時点でかなり一方的、普通の人なら戦略的撤退を考えるところだ。しかし、アルトは敗北を認めるを良しとせず、ひたすら、垂直跳びの練習に明け暮れていた。
そして、二十分が過ぎた……二十分もやるなよという意見は非常に正しいが、それはアルトに言っていただきたい……ついに彼女は大空の住人に戻ることが出来た!
……かのように見えた。次の瞬間、再び、顔面から床にたたきつけられる愛らしい妖精さん。勝利の空から、恥辱の大地へと引き戻される。これこそが本当に一方的な戦いの幕開けだった。
飛び上がっては叩き落とされる、叩き落とされては再び飛び上がる、激しい上下運動。往復するたび、アルトの体に生傷が増えていく。もはや、戦いではなく、単に遊ばれているだけ……幽霊に遊ばれる妖精……シュールだ。
ビタン! ばたん! グシャッ!
と、言うわけでここの冒頭へと戻るわけ。
「満足したか?」
何度も何度も地面に叩きつけられた哀れな妖精、その体を広上げ、良夜はパンパンと汚れたドレスの裾を払ってやった。
「まっ、まだだわ……ちょっちょっと休憩するだけなのよ!」
「……お前、余裕あるな……」
「はぁ……はぁ……あるわよ、まだまだ、戦えるわ」
羽を摘んでジロジロとアルトの体を見渡す……何回もコンクリートの床にたたきつけられた割りには怪我が少ない……丈夫に出来てる奴だ。
「なっなによ……今、良夜の……相手、してる暇、ないの」
「全く……暇な奴だな……」
「うるさい! 今、息……整えてるんだから、静かにしてて……」
そう言うとアルトは、良夜の手から逃れ、彼の頭の上で大の字になった。しばらくは声を掛けても返事をしないだろう。
さっきまでも暇だったが、これで更に暇になった。良夜は、アルトの息が整うまでの時間、良夜は彼女が一方的に嬲られていた場所……じゃなくて、激戦を繰り広げていた場所へと視線を向けた。
相変わらず、何も知らない人々がパンを手にとってはそこから離れていく。ごくごく日常的な風景、幽霊が居るとか、妖精がその幽霊に弄ばれていたなんて事、誰が想像しているだろうか? そう考えると、ちょっとした役得とも思えなくもない。
良夜がぼんやりと時間を潰していると、そこへエプロンを身につけた一人の人間がやってきた。見慣れたエプロンはこのスーパーの制服、彼は回りをキョロキョロと見渡すと、隠し持っていた塩をそこにぱらっと落とした。
あちゃ……良夜は思わず天を仰ぎ見た……ら、頭の上で寝てる奴は落ちて当たり前。
「ちょっと! 人が休んでるときくらい、大人しくできないのかしら?」
ずり落ち掛けたアルトは、慌てて良夜の髪を掴んで抗議の声を上げた。
「……塩、撒かれた」
短く的確な言葉で彼女の戦いが、第三者の手によって打ち切られたことを告げる。
「うそ!」
今度は彼女が慌てる番だ。アルトは髪を掴んでいた手を離すと、トンと良夜の肩を蹴って戦場へと、いや、もう「古戦場」と言った方が正しい場所へと羽ばたいた。
「……居なくなったのかしら……」
何度も叩きつけられた床へと視線を落とし、名残惜しそうに彼女はつぶやき、嘆息した。
「多分な……また、今度連れてきて――」
ビタン!!
完璧、かつ、受け身すらとる暇もなく、床に叩きつけられる小さな体。痙攣してない……今度こそ死んだか?
「……良いわよ、貴方が逃げないんなら、私も逃げないわ!」
どっこい生きてる妖精さん。彼女は埃だらけ傷だらけ、ついでに鼻血だらけの顔を上げて毅然と叫んだ。その顔が何処か嬉しそうに見えたのは、多分、気のせいではないだろう、と良夜は思った。
「あぁ……終わったと思ったんだけどな……」
買いもしない冷凍ケースにもたれかかり、良夜は諦めたような口調で呟いた……昼飯時までに終わればいいのだが……
アルトは本当に逃げなかった。良夜に助けも呼ばず、ただ、ひたすらに床に叩きつけられること、小一時間……やってる方もアレだが、見ている方もアレだ。
終わりの時間は唐突にやってきた。
もはや何度目かすら数えるのがおっくうになるほど、アルトが床に叩きつけられた後のことだった。相変わらず、彼女は逃げもせず、休みもせず、宙へと舞い上がりと叩きつけられる力に耐えようと全身を強ばらせ、その時を待った。
しかし、いつまで経ってもその時は来ない。アルトの体は浮き上がったまま。
「あれ……逃げたの?」
恐る恐る体の力を抜き、アルトは回りの風景を見渡した。もっとも、最初から幽霊の姿なんて物は見えていなかったのだ。いくら回りを見渡したところで、幽霊がアルトの油断を誘っているのか、飽きてしまったのか、逃げてしまったのか、答えを示す何かが見つかる事はない。
「飽きたんだよ、お前がだらしないから」
小一時間も寄りかかっていた冷凍ケースから離れ、アルトのそばに良夜は近付いた。面白い物ではあったが、一時間以上も付き合っていれば流石に良夜も飽きてしまう。
「ふっん! 私の忍耐強さが勝ったのよ」
そう言って胸を張るアルト、彼女はボロボロになった体を引きずり、良夜の頭の上へと着地を決めた。
その時だった……
『ありがとう』
そんな少女の声が良夜の耳に届いた。
「聞こえたか?」
「……ありがとうって言ったわ……小さな女の子」
「成仏した……か?」
「多分……ううん、きっとそうだわ」
はっきりとした口調、アルトは自信を持った声でそう言いきり、良夜もそれに反論することはなかった。
と、思ったんだけどなぁ……
真昼の決闘から二週間ほどが過ぎた。
「あれからな、誰も肩が重くなるって言わなくなったよ」
「そう……やっぱり、成仏したのね」
誇らしげな顔の妖精とは逆に、バイト大学生の顔は暗い。
「いいや……俺にだけ『呼んで』って声が聞こえるようになった……どーしてくれるんだよ!!!!」
「知らないわよ! もう、いやよ! 私、あれから三日も寝込んだのよ!!!」
と、言う会話が喫茶アルトいつもの窓際隅っこの席で交わされましたとさ。